 |
|---|
| ���m�͖�̗E�p�i�̕i��@�O�N�悭�j |
����22�N4��16���@�Z������
�y���u��v�S�O�N�ڂ̒�����
�r�c�@���M
 |
|---|
| ���m�͖�̗E�p�i�̕i��@�O�N�悭�j |
���@���C�e�p����ڑO�ɂ����C���
���a19�N10��25���ߑO�S���A�ˑR�Ƃ��Đj�H180�x�A����18�m�b�g�ŁA�T�}�[���������C����q�s���Ă����B�������烌�C�e�p�������ƂU���Ԃ̋����ł������B
��10������͂ł���y���u��v�̊͋��́A���v��̕����Ղ̌u���h�����������Ȍ�������Ă���ȊO�͊��S�ȓ��Ίǐ����~����A�����E�����悤�ȋْ����݂Ȃ����Ă���B
���X�����X�R�[���̊Ԃ��猩���鐯���A�₽��ɋP�������Ǝv���Ƃ��������悤�Ɍ����Ȃ��Ȃ�B
����V�u�����C�ł̐퓬�ŌI�c�͑��͐�́u�����v�����������A�u��v���G�͍ڋ@�̓x�d�Ȃ�}�~�������ɉ�A�E���͎�̐��ʒ���ɒ��a�S���[�g���A���̕t�߂̌����ɑ召�����̔j�������������Q���A�Z���̊�@�ɕm�����B���̉��}�C����s���s�x�ōs�Ȃ��Ă����̂�����Əo���オ�����炵���A���}�w���������܂݂�ƂȂ�A�Ⴞ�������炬�炳���Ċ͋��ɂ������Ă����B
�����āA�u�͒��A�O���j�E�̉��}�C���A�������܂����v�ƕ���ƁA
�u���m�b�g�܂őς����邩�v�Ɗ͒��������Ԃ����B�����ŁA
�u28�m�b�g�܂ł͑��v�ł����A30�m�b�g�ȏ�͖����ł��v
�Ɠ�����ƁA�͒��́A
�u30�m�b�g�ȏ�o���Ȃ���ΐ퓬�ɂȂ�v�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�ƌ����Ėق��Ă��܂����B
�����m�푈�̏��킢�炢�������̐퓬��̌����Ă���g���^���͒��́A���イ���イ���}�w�����ȉ��̉��}���B��10�����Ԃɂ킽����ȓw�͂�m���Ă���B�����Ă���ȏ�̏��u�͏o���Ȃ������������Ă���̂ł���B
�u�퓬�ɂȂ�v�Ƃ����͒��̋C���́A���}�w�����ɂ��ɂ��قǂ悭�������Ă���̂ł���B���̌��t�̗��ɂ͂��悢��ƂȂ�A30�m�b�g�ȏ���o���Đ퓬���A�G�Ǝh���Ⴆ��o����߂Ă���̂��B
�ߑO�T���A��������炸�j�H180�x�A����18�m�b�g���B�S���퓬�z�u�ɏA�����B�ܘ_������炸���Ɛ퓬�z�u�ɏA���Ă���̂����A��Ԃ͔��������ꂼ��̔z�u�ŋx�߂̑Ԑ��ɂ������B���悢�惌�C�e�p�����߂��Ȃ�A�������퓬�z�u�ɏA�����B
�����������Z�ł�������l�����m�̉����ؕ������́A�u�����z�u�ɂ��v�̍��߂ɂ��A�������Z�̔C�����q�C�m�ł��鎄�ɐ\���p�������āA�e�Ζ�Ɍ����̌�����n�����B�i�����퓬�z�u�ł́A�q�C�m���������Z�̔C�����s���j�B���̉����ؕ������́A�R���Ԍ�ɂ͂��̐��̐l�ł͂Ȃ��Ȃ�^���ɂ������B
�ˑR�A�X�R�[���͊͑����Ď��E�͋ɂ߂ĕs�ǂł���B�ؑ��i�ߊ��A�g���͒����n�ߊ͋��ɂ���҂͖ܘ_�o���ȗ��N���ꐇ�����Ă��Ȃ��B���B�͂قƂ�ǔ�J����m�o���Ă��Ȃ��B�u���l�C�̊�n���o�����������ȗ��A�_�o�͐키���ƈȊO�̈�̊��o��Ⴢ����Ă���悤�ł���B
�ߑO�U���A�j�H�A���͂Ƃ��ˑR�Ƃ��ē����B�X�R�[���̂��ߓV���͕s�\�Ȃ̂ŁA�q�Վ����ɂ��ߑO�U���͈̊ʂ��C�}�ɋL������B�悭�̏���N�����Ă��������͍��������̓w�͂ɂ���č���͋ɂ߂čD���ł���B
���C�e�p���܂ł���100�C���ł���B���̂��߁u10�����̂P�؊����������Ă����v�ƍ��������ɖ�����ƁA�ނ́A�u10�����̂P�؊��X�����v�@�u�쓮�ǍD�v�Ɠ`���ǂ�ʂ��Č��C�ȓ������Ԃ��Ă���B
���@�����u��a�v�̂S�U�Z���`�C
�ߑO�U�����ɂȂ�A�T�}�[�������̊C�ʂ͎���ɖ��邭�Ȃ�A�X�R�[��������オ���Ă����B�s����O���̐��������A���Ă��ɐԂ����މ_�ƊC�Ƃ̋��Ɏ���ɖ����ɔF�߂���悤�ɂȂ��Ă����B
���̎��A��l�̌������̑o�ዾ�͋z�����܂��悤�ɐ������̈����_�Ɍ�����ꂽ�B
�u�}�X�g�炵�����́A��65�x�A�������v��
�͋��㕔�̓`���ǂ��Î��j�����B
�u�G���v
�i�ߊ��A�͒��ȉ��A�����̊�͈�l�ɑo�ዾ��ʂ��č�70�x�̐������ɋz���t����ꂽ�B������Ɏ�Ɋ|���Ă���V�{�o�ዾ����ɂ����B
������B�������ɓG�͑D�Q���A��������ɋ͂��ɏo�Ă���}�X�g�̐��͂U�{�B�����ɓG�����̐M����g���A�����Ɋ��́u��a�v�ɕ����B
�u�G�炵���}�X�g����B����110�x�A�����Q��6000���[�g���v�I�c�͑��́A�������G���`������Ă����B
��锼�A�T���x���i���W�m������ʉ߂����̂��A�u��P���G�q�s����ɐ�ʂ���v�Ƃ������́u��a�v����̐M���ɂ��A�͑��͉�����1000���[�g���Ԋu�ŕ��сA�G����͒������߂ăT�}�[����������H��ցA���C�e�p���Ɍ����Ă����̂ł���B���̍ō����O�[�ɐ�ʂ��Ă�����10������́u��v�͓G�ƍł��߂������ɂ���A�]���Ĕ��������������̂ł���B
�u��10�퓬����ɐ�ʂ���B����24�m�b�g�A�ő�푬�A�����ҋ@�ƂȂ��v
���́u��a�v���S�͂ɑ��Ė��߂�������ꂽ�B����܂ł̍��G�����肸���Ɩ��W�����C��퓬�Ԑ������ꂽ�B�e�͎͂��Ă�U������̑S�Ă�G�͑��̕����Ɍ������B�Ȃ��ł��u��a�v�̎�C�́A�ł��������̎˒���L���Ă���B�₪�Ă��̋���ȖC���́A�X���ĂɖڕW�Ɍ����Ă��̉ΊW���J�����B
���a19�N10��25���A���̂悤�ɂ��ă��C�e�����ł̒����P���̖������ė��Ƃ��ꂽ�B�u�I�c�͑��i�]�̔��]�v�Ƃ����郌�C�e���C��̒��̂��Ƃł���B
�u��a�v�̑�R�Ď˂��ł��o���ꂽ�̂Ɩw��Ǔ����ɁA��́u����v�u�����v�u�Y���v�̖C�傪�����B���̍������R�C��́A����̍J�Ɖ������B�G��͂͂����G�@�͎Փ�I�c�͑��̓���ɏP���|�����Ă����B
�u��v�̎�C�A���p�C�A�@�e���Q����悤�ɏP���Ă���G�@�ɂ��̖C�𗁂т��A�����ނ���悤�ɂ��Ȃ���G����͑��𔗂��Ă䂭�B
�u��v�ɍU�����Ă���G�@�̕����Ƌ@���K���ɕ��錩�����̐��𗊂�ɁA�����ɉ�𑀊͂���q�C���A�͑S�ʂ̎w�����Ƃ�͒��A�퓬���w������i�ߊ��B�퓬���̊͋��ł́A���̓I�����͏��Ȃ����ڂ܂��邵���ω�����ɓI�m�ɔ������铪�]�A���f�́A�Ԕ������Ȃ��ӎu���肪�v�������B
���͓G�����̍��X�ƕς��Ԑ��A�G�̍U���A�킪���̐퓬�A�͒��̖��߂ȂǁA���̎����Ɠ��e��v�̂悭�퓬�L�^�Ƃ��ċL���������A���͑�a�Ƃ̐M���̎���A�u��v�͈̊ʑ���ȂǍq�C�m�Ƃ��Ă̐E�����s�ɑS�_�o���W�����A������������B
�Z�@��u�ɏC����Ɖ������͋�
�ߑO�V��25���Ɍ㕔����������u�O���}���R�@�}�~���v�Ɠ`���ǂ�ʂ��ăJ�������������Ă����B�͂́A���傤�ǒ��O�̓G�@��������āA�����ł���B�Ԑ�����]���ΉE�ɉ�����ׂ��Ƃ���ł��邪�A���Ɏ��ǂ̑ė͂ł��ɉ��Ă��邽�߁A��Y�q�C���͙�l�̔��f�Ŋ͒��Ɂu���̂܂܍��ɉ�����܂��v�ƕ��Ď�Lj�t��߂����B
���͎��̏u�ԁA����̐퓬�ő̌������}�~���̔��e�����ɂ�鍌���ƌ����Ƃ�\�������B
�������A�G�@�͈ӊO�ɂ����e�𓊉������A�������܂������𗧂Ăċ@�e�|�˂��͔�����͎�ɂ����ė��т��Ă����B�ނ�́A�ˑR���ꂽ�I�c�͑��ɋ����Ĕ��e�⋛��������]�T���Ȃ��Q�Ăĕ�͂͂����̂ł���B�u��v�͏�ŁA���߂Ď��G�@�̋@�e�|�˂ł���B���B�͊͋��̎Օ����ɉB��g��������B���łQ�ԋ@�̉g���e���͋��̑��K���X��j�A�����͋��̍b��^���ԂȃX�W�������āA�J���J���Ƌ������𗧂ĂĔ�щ�����B
�͂̑�C�͖C�g���ł��������ɉ��Ă���B�R�ԋ@�̏e���������Ă���͂����̐j�H�ɗ��Ē������B
���̏e���ɂ��A�����͋��Ŏ��̍��ׂɗ����Ă��������ؕ������́A��l�ɕ��������A���x���������^���ԂɏĂ���7.7�~���̋@�e�e�����āA�ނ̑�ڕ����畠���֊ђʂ����B���̏������琁���o�����N���́A���̐퓬���̃Y�{���ɑ��ʂɔ�юU�����B�u���ꂽ�v�Ԃ₭�悤�Ɉꌾ�]��������A�݂�݂�o���̈א��߂������x�����グ����������ƌ��߁A�Ԃ��Ȃ�����Ɠ|�ꂽ�B
�ނ̌����ׂ�̐����ȕ��ʔՈ��̉��m���P�l�ƕ��Q�����r�A�����ɂ��ꂼ��ђʏe�n���A���̏�ɂ������ɓ|��Ă���B
�͋��͍����ɂ��Č��̊C�Ɖ����A���L�����S�ȏL�����������B�����ɑ��͂���q�C���̐퓬�X�̃A�S�Ђ��ɂ͕����҂̓��Ђ���сA�N���ƂƂ��ɂׂ��Ƃ�ƕt�����Ă���A���͍ŏ��A�q�C�������������̂��Ǝv�����B�������A�͒����q�C������F��ς����A��ÂɓG�̍s�����ϑ������͂ɗ]�O���Ȃ��B
���́A�f�����퓬�L�^���L�����Ă���A�����ؕ�������M�����ɔw���킹�Đ펞���Î��ɂȂ��Ă���m�����֍~�낳�����B�����A�����ނ�����N���������A�ނ͊��Ɏ���Ă����B
���̏e���́A�u��v�ɂ����鎄�̗B��̃N���X���[�g�@�i�C��72���j�ł���ɓ���ǗY���тɂ��A���̖����L���Ă����B���p�C�w�����ł���ނ́A�͋��z�u�̎��Ƃ͒���������10�����[�g����������Ă��Ȃ������B�����������A�ނ̏d����m�����̂́A�[���A10���x�ɋy�Ԕg��I�ȓG�̗��P���ꉞ���܂��Ă���ł������B
�����Ĕނ́A�������t�����͑����X���[�C�ɓ��B�������A21�̐��U������B
25���A�ŏ��̋�P�́A�e���݂̂ł��������A�₪�ė����������������V�����G�@����������̍U�����A�I���A�I�c�͑�����ɏP���Ă����B
���̓��A�S�x�ڂ̔g��U���������̂��Ƃł���B
�u�͎�}�~���v
�ƌ�������̔����ɂÂ��A
�u�ʑLj�t�v
�q�C���̉s���R���������������͍��߂ɂ��A�͂����ɌX���E�ɉ��n�߂�ƊԂ��Ȃ��A���ɋ����A�������悤�ȍ����Ɛg�̂����o�����悤�Ȍ������͑̂̓��h�ŁA�͋��ɂ������l���́A���߂��|�ꂽ�B���̏u�ԁA���K���X�̔�юU�鉹�A�\�����̔j��鉹���C���Ƌ��Ɏ��̌ۖ���j�����悤���B
�����琅�������Ԃ����̂����̎��ł���B
�ۖ��ی�p�̎����́A�������ł����B�C�}��͔j�Ђł��������ɏ����A�g���Ă�����K�ƃR���p�X�͎g�����ɂȂ�Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B
���̎��A�͋������ɂ����������ł���k�앺���́A���ߒe�̔j�Ђō��r�����̂���������������d�������B����12�Z���`���p�o��]�������A���NJђʍE�̑����������g�p���s�\�ƂȂ����B�ނ͎c��E��ƌ��ƂŁA�ؒf���̏㕔���тŊ����A�o���O�ɌR�㒷���������ׂĂɋ�����ꂽ�ʂ�|�̎~���_�Ŏ~�������āA�����w�����ɂ��̎|����Ă���B���̐��͕����Ɩw��Ǖς���Ă��Ȃ������B
����12�Z���`���p�o��]���������ɏq�ׂ�ʂ�A������̂��Ƃ�40�N�U��ɕ��Ɍ��犠�̒n�Ŏ��ƍĉ�邱�ƂɂȂ����̂ł���B
���@�o�ዾ�ƂȂ����������
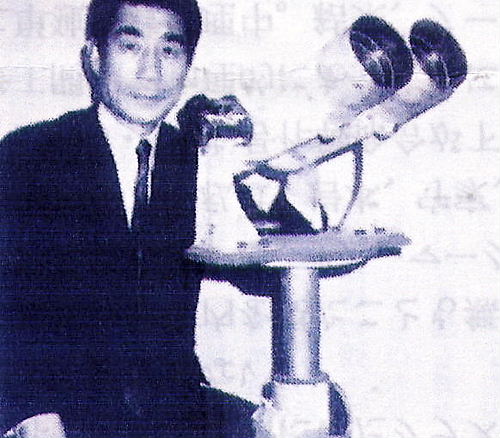 |
��P�QCM�o�ዾ �Ƃ����Ă̒r�c�q�C�m |
|---|
�b�����݂ɖ߂����B���N�A���Ȃ킿���a59�N�R���A�����{�v�������̑�\������Ƃ��Ď����A���Ђ̑��x�ЂŐv�������w�@��w�犠�L�����v�Z���^�[�̏v�H���ɎQ�����̂��Ƃł���B���R���Ɍb�܂ꂽ���̃L�����v��͍L��ȕ~�n�ŁA���n�����i�͐��ɑf���炵�����̂ł���B
���̓����~�n���̂قlj�����ʏ������u�̏�ɁA���Ɋ������A�g���Ă���Z�~�i�[�n�E�X������B���܂ő������Ԃ��������̂ŁA���łɂ��̎{�݂����w�����Ă�������B
�����ē����Ă��ꂽ���Ђ̓����x�В����A�ˑR���Ɏv���������Ȃ����t���������̂ł���B������w�̎{�ݕ����������̘b�ɂ��ƁA���̌����̉���ɂ���]�����͋����{�C�R�̌R�́u��v�͏�ɂ��������̂��Ƃ����̂ł���B���͎v�킸�����^���Ă��܂����B
����͑S���M������ł������B�Ƃ��������̖]�����Ȃ���̂������Ă�������B�m���ɂ���́A�푈���ɋ��C�R���p���Ă���12�Z���`���p�o��]�����ł������B
�������A�R�́u��v�@�̕��ł���؋��͉�����������Ȃ��B
��10������́u��v�́A���C�e���C��ɂ����Đ펀��47���A�d�y����97�����o���A�͔͑̂����ɂ���Q�ŏ����炯�ɂȂ�Ȃ����10��28���A�Ăуu���l�C�p�ɋA�����邱�Ƃ��o�����B
�������A���̊C��œ��{�C�R�̐���͒��͉�œI�ȑŌ����A�͑��Ґ��͑啝�ɏk�����A�ĕҐ���]�V�Ȃ����ꂽ�B�u��v�����͂Ƃ����10��������U����������Ȃ��Ȃ�A���̊C��Œ��v�����o���́u�\��v�ɑ����đ�Q��������̊��͂ƂȂ�悤�A�A���͑������̖��߂��������B
�����ď��t������́u��a�v�u����v�u�����v���Ƌ��ɎP���̋쒀�͂𗦂��ē��n�Ɍ��������B�r����p�̉������q�s���Ă��鎞�A���������̍Œ��œG�����̗͂����ɑ����A��́u�����v�ƁA�쒀�́u�Y���v�������A�悤�₭�̎v���œ��n�ɋA�������̂ł������B
�����Ď��̐퓬�ɔ����邽�߂ɁA�����ɐl���̕�[�Ɗً͑̂̋}�C�����A�����ɂ��ōs�Ȃ�ꂽ�B�j���ӏ��͑召���킹�Ĉ����z���Ă����Ƃ������Ƃł���B
���̊Ԃ��A��ǂ͈���I�ɂ킪���ɕs���ƂȂ�A�͑��̑Ԃ��Ȃ��Ȃ����{�C�R�̎c���͒��́A�X�Ɉ����͓���C��ŁA���邢�͐��˓��Ŏ��X�Ǝ����Ă������B�����ď��a20�N�S���A�G������ɏ㗤����ɋy�ѓ��{�C�R�Ō�̌���ƂȂ�������C����U���ɎQ���ł���͒��́A��́u��a�v�ƁA�y���u��v�����͂Ƃ����Q��������̋쒀�͂W�ǂ�����݂̂ƂȂ��Ă����B
���@�����D������������o�H
���a20�N�S���U���A�y���u��v�͐�́u��a�v�A�쒀�͂W�ǂƂƂ��ɓ��R�����o���A���V���A���P����G�͏�@�̉���ɂ��y�Ԕg��U���ɉ�A��a�͒����e21���A�����V�{�A���ߒe�����������ނ�A�ߌ�Q�����A���V�i�C�ɒ��v�����B
�u��a�v�̒��v�ɐ旧����12���A���U�͑�10�ǂ̂����쒀�͂S�ǂ��c���A���͑S�Č�������A���͒��~�ƂȂ����B
�u��v�̐펀�҂͕����ȉ�446���ŁA�c��̐����҂͓��v�̂̂��A���v��Ƃꂽ���͂ɋ~������閘�A�G�@�̊C�ʂ��ꂷ��̋@�e�|�˂ɂ��炳��Ȃ���A�d���̗��o�����C��ɕY�����Ă����B�������̒��̈�l�������B�Ղ͎c���Ă��鐔�t�̎ʐ^�݂̂ł���B
�b���Ăь��݂ɖ߂����B�Z�~�i�[�n�E�X�̖]�������Ȃ��A�u��v�̂��̂��Ƃ�����̂��A���͑������������ɂ��̌o�܂�q�˂��B
����ɂ��ƁA�u���N�O�A���w�@��w�̂n�a�����������w�Ɋ��ꂽ�v�Ƃ����B�����ʼn��́A�������̎茳�ɂ������̂����ځA�������ɂ�����āA���̂悤�Ȏ�����f�����Ƃ��o�����B
�I�풼��A�i���R���L���E���ɏ㗤����O�ɁA���C�R�H���̑��D���́A������Дd�����D���Ɉ����p����Čo�c���邱�ƂɂȂ����B
�������͓����d�����D���̎Ј��ł������̂ł���B
�]�����ȂǍޗ����i�̈����n���́A�Njƕ������R�卲���������Ă����B�d�����D���́A�I��܂ŌR�Ђɂ������C�R��v�������{�����S�����Č������B�S�Ă̍ޗ����i�́A�C�R���̍ɕ\�ɂ��ƂÂ����i�Əƍ����Ĕd�����Ɉ����n���ꂽ�B�S���̐l�����A�C�R�ݐЂ��̂܂܂Ɉ����p����A���ׂĂ͔\���悭���^�ꂽ�Ɠ�������z���A�������͘b���Ă����������B
���̎��A���i������j�̖]�������A����Ȃ�Ə��Ǒւ����ꂽ�킯�ł���B���̌�A���鎞���ɔd�����D���ł́A�C�R��������p�����ޗ����i�����邱�ƂɂȂ����B�푈���I���A�펞���̕K�v�i�����͕s�v�ƂȂ������������������͓̂��R�ł���B�����̐��������ɂ������āA�������̕��������̖]���������Q���Ă����Ƃ������Ƃł���B
�������̉Ƃ͌��̍���ɂ������̂ŁA�����̎R��A�R���̉Ƃ�A��͓V��߂��肵���Ƃ����B���̌�A�d�����D�������D�ɂ����A�����̏����ɏA�C���ꂽ���A���݂͈��ނ���80�������ċɂ߂Ă����C�ł���B
�������A�Ȃ����̖]���������C�R�H���ɁA�I�펞�ɂ������̂��H�@�܂��ˑR�Ƃ��ĕs���ł���B�����Ŏ��́A�u��v�̐����҂ɓ����āA���̎����̗L���ׂ邱�Ƃɂ����B
���́A������U�̎��́u��v�̑�S�����������I���ł��������A���a18�N�̏H�A�܂��~�����̐V�s�y���u��v�ɒ��C���Ĉȗ��A��19�N�U���̃}���A�i���C��A��10���̃��C�e���C��ɎQ�����������́A�q�C�m�̔z�u�ł������B
�����p�ዾ�́A���ׂčq�C�m�̊Ǘ����镺��ł���B�K���A���̕����ł��������������̈�㕺���́A���݂����݂ŁA�����⍇�킹���Ƃ���A�ނ��玟�̎���m�邱�Ƃ��o�����B
����́A�O�q�����k�앺�������r�������Ƃ����d���������ɁA�j�������o�ዾ�����C�e���C�킩����n�ɋA����ɓ��`�����ہA�������������ł�������鐭�v�����ɖ����Č��H���ɏC���̂��߂Ɏ��Q�������Ƃ����̂ł���B
���̘b���A���ɂ��������ȋL�����h��A�����́u��v�̐퓬�ڕ�ׂĂ݂��B
���̒��̕���̏ጇ�������\�Ɂw12�Z���`���p�o��]�����x�@�u���NJђʍE�̑����A�͓��ɂďC���P���Ԕ��ɋy�Ԃ��s�\�A�@����A�H���C����v���v�Ƃ���B��㕺���̏،��Ɛ������������Ă����̂ł���B
�͂̌����p�o�ዾ�ɂ́A���ꂼ����p�x������B��Ɋ͂̑S���ʂ����S�ɃJ�o�[���Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���̈�������邱�Ƃ́A������Ɏ��p�������邱�ƂɂȂ�B
�H���ŏC�����Ă�����Ԃ����p�̂܂ܑ҂�ɂ͂䂩�Ȃ��͓̂��R�ł���B
�����ŋ��炭����̑o�ዾ���u��v�ɐ��t���A���̑o�ዾ�͎傪���Ȃ��Ȃ����܂܌��H���ŏI����}�����̂ł��낤�B
�����Č����D�����������̎���ւĘZ�b�R�A�犠�̊��w�@��w�Z�~�i�[�n�E�X�̉���ɐ����Ȃ��炦�āA���ƍĉ�邱�ƂɂȂ����̂ł���B
���@�������킯����̃G�s�\�[�h
���̑o�ዾ�ɂ́A���܈�̃G�s�\�[�h������B�j�������o�ዾ�����H���Ɏ��Q������镺���́A���̓��C�e���C��̌�A����Ζ�����]���Ă���A�ފ͂�\�肳��Ă����̂ł���B�Ƃ��낪���ɓ��`�����ہA���܂��ܑ�镺�������̑o�ዾ������čH���ɍs���Ă���ԂɁA�͓��Łu�ފ͗\��ґ�����b�ɏW���v�Ƃ����w�߂��o���ꂽ�̂ł���B��ǂ̋}�ςŗ���̖h�����̕�[���}����Ă���A��ꂩ��A�������R�͂̐l����҂��\���Ă����̂ł���B
��镺�����s�݂̂��߁A�ނ̏������Ă�����V�����ł͑ފ͗\��҂̈������P���s���ƂȂ����B�����ő�镺���Ɠ����̕��������ފ͂�\�o�āA��镺�����H������A�͂������͊��ɑފ͎ґS�����͂��~��Ă��܂����Ղł������B
����Ζ��ɕς��鎖��S�҂��ɂ��Ă�����镺���́A�Ăъ͂Ɏc�����H�ڂɂȂ��Ă��܂����B
�����ď��a20�N�S���A�ނ̐��܂�̋��ł��鉫��ɓG���㗤����ɋy�сA�u��v��g�݂Ƃ��ĉ�����U���ɎQ�����邱�ƂɂȂ����B
�ފ͏o���Ȃ��Ȃ��������́A�s���ȋC�����Ԃ��Ă����ނ��A���悢����U�ƌ��������͋��y�ɍ��߂�o������A���킸�^����ꂽ�^���ɏ]���S���ɂȂ��Ă����B
���̔ނ͏�́u��v�����v�����̂��A�Y�����Ă��鏊�𖡕��쒀�͂ɋ~������A39�N��̍����A���y����ŕ��a�ȉƒ�Ɍb�܂�A���B�Ɉ͂܂��70�̐l�����Ȃ����j�ƕ邵�Ă���B
����A�ނ̑���ɑފ͂�\���ł��������́A��]�ǂ���͂�肸���ƈ��S�Ǝv���Ă�������Ζ��ɂȂ������A�z�����ꂽ�̂̓}�j���h�����ł������B���̒����ŁA�ނ͂����Ő펀���Ă��邱�Ƃ����������B
�^���Ƃ������̂́A�l�Ԃ̈ӎu���]��y���ɒ��������̂ł���B
�i�ҎҒ��A�{�e�͎G���u�ہv�A59�N11�����\�ʊ�460���\�Ɋ�e���ꂽ���̂��A�u�ہv�ҏW���̍D�ӂɂ���āA�]�ڂ������̂ł�
�i�Ȃɂ��j���[�X52��16�Ł@���a60�N�R���f�ځj