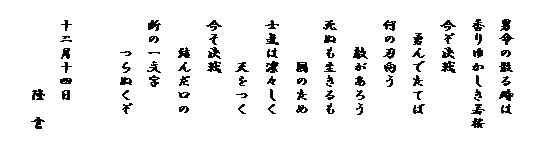 |
平成22年4月29日 校正すみ
米護衛空母に突入した特攻隊員の遺族を捜せ
菅原 完
はじめに
夕日に映えて点在する断雲の間から、その特攻隊員は零戦の風防越しに、南シナ海の蒼い海面に現れてきた敵艦を見つめた。敵艦は波立った海面に白い航跡を引いて、彼がマバラカット基地を発進後、探し求めていた目標の存在を示していた。遂に見つけた。目標はルソン島の西岸から約50浬沖、リンガエン湾の南南西を北上していた。彼は安堵すると同時に、敵戦闘哨戒機にも発見されず、ここまで辿り着いたことに満足感も覚えた。数分で彼の生命は終わろうとしている。時に1945(昭和20)年1月5日1745頃 ・・・・・
太平洋戦争の末期、1944年10月下旬から比島方面において開始された特別攻撃隊による体当たり攻撃は、沖縄戦においても継承され、終戦の8月15日の午前まで行われた。この間、特攻により散華した若者の数は、陸・海軍あわせて三千数百名にのぼるといわれている。
しかし、彼らについて分かっていることは、何月何日、何時何分、どこそこ方面の敵を攻撃するため、どこの基地から出撃、なかには不確実ながら戦果が書かれている場合もあるが、たいていの場合それだけで、彼らの最期がどうであったと触れているものは皆無に近いといっても過言ではない。
奇跡的に、その最期が判明した特攻隊員は、日米双方の資料に基づく状況証拠によるものか、あるいは米側が拾得した遺品を、拾得者またはその遺族が、後日特攻隊員の遺族を探し出して返還した場合である。このようにして特攻隊員の最期が判明している事例は、筆者が知っている限りでは、十数件に満たない。
帝国海軍中尉丸山隆
本篇の主人公の一人である丸山隆(ゆたか)は、1922(大正11)年2月21日、石川県北部の七尾市で生まれた。そして1940(昭和15)年12月1日、広島県江田島にある海軍兵学校に72期生として入校した。
すでに欧州においては、前年9月独逸と英・仏の間に戦争が始まり、日中戦争(当時は「シナ事変」といった)も3年目に入ったが、解決のメドがたたぬ泥沼状態であった。大学、高専に進学しても、いずれは徴兵で軍隊に採られる時代のことでる。国をあげて戦時体制に傾斜していた当時、陸士か海兵は、健康で学力に秀でた若者が当然進む道であった。
また、この年9月には、日本軍が北部仏印に進駐し、日独伊三国同盟が締結され、太平洋戦争に向けて、日本がブレーキの利かない車のように、下り坂を転がり始めた年でもあった。そして、後日彼が爆装して出撃することになる零式艦上戦闘機「零戦」が、正式採用されたのもこの年である。
海軍生徒時代の丸山の写真を見ると、私財をなげうって貧しい山間部の子供たちに教育を施した父親と、自らも教鞭をとって、その夫を助けた母親の血を引いているせいか、海軍士官の卵というよりは、もし戦時下でなかったら、彼は学者か、学校の先生になっていたのではないかという雰囲気を漂わせている。当時の丸山について、朴訥、温厚、純情という同期生の寸評がある。
兵学校生活のうちで一番辛い三号生徒(一年生)の一年間が終わり、73期が入校して待望の2号生徒(二年生)に進級した翌1941(昭和16)年12月8日、日本海軍の真珠湾攻撃により太平洋戦争の幕は切って落とされた。日本軍は東南アジアの各地を瞬く間に席巻し、全国津々浦々まで戦勝気分が横溢したが、草鹿任一校長は、「生徒の本分は常に不変である。今までと同じように勉強せよ」と諭し、生徒館での生活には何の変化もなかったという。
その数年前までは4年制であった兵学校の教程は、国際情勢の緊迫に伴いすでに3年制に短縮されていたが、72期の場合、戦局の悪化に対処するため、さらに3か月繰り上がって、卒業は1943(昭和18)年9月15日である。
遠洋航海もなく、卒業生625名のうち、艦船班314名は2ヶ月間の実習艦隊乗り組みを命ぜられ、「伊勢」「山城」などに乗艦したが、丸山たち航空班311名は、艦隊勤務の経験をまったく持たないまま、第41期飛行学生として、霞ヶ浦航空隊において93式陸上中間練習機(赤トンボ)による教程を開始した。
1943年に入ると、ガダルカナル島からの撤退、山本五十六連合艦隊司令長官の戦死、アッツ島の玉砕など、戦局は次第に敗色を深め、彼らが一日も早く戦力になる日が切望されていたのである。また、丸山個人にとっても、母きぬが他界した年であった。
霞ヶ浦での約5ヶ月にわたる練習機教程を終え、少尉に任官した丸山たち72期生は、その後、これも5ヶ月にわたる戦闘機専修学生として実用機(零戦)教程を鴻之池航空隊において終了し、14名が筑波航空隊に教官として配置された。そして9月15日、中尉に昇進した。
当時、丸山とともに厳しい訓練を受けた新庄浩氏(東京都在住)は、丸山は真面目で寡黙な性格、信頼する親友の一人であったといわれる。実用機教程も終わりに近づいた6月、丸山のすぐ上の兄寛陸軍中尉が、西部ニューギニアのビアク島において、一式戦闘機(陸軍の「隼」)10機を率いて連合軍の揚陸点を攻撃した際に戦死している。
特攻を志願する。
新庄氏によると、8月のある日の夕刻、先輩の教官や下士官の教員とともに飛行場に集合を命ぜられた。司令と飛行長が来て、妻子のある者、長男、一人子は解散するように命じた。
そこで残った者に戦局の重大さを説き、これに対処するため、海軍としては生還を期すことはできないが、一機一艦を屠る新兵器による特攻の採用も考えざるを得ないとの話があり、志願する覚悟のあるものは挙手するようにいわれた。緊張感が漲ったが、一瞬おくれて総員が挙手した。
丸山が第一線に向けて出陣するのは、これから3ヶ月余り後のことである。内藤初穂著「桜花」非情の特攻兵器(文芸春秋)によると、特攻志願者の募集が8月中旬となっているので、新庄氏のお話は、時期的に見て「桜花」隊員の募集だったのであろう。
丸山が比島にあった第201航空隊への転勤を命ぜられるのが11月21日である。当時、零戦を25番(250キロ爆弾)で爆装した「爆戦」による特攻の搭乗員は、すべて201空に移籍し、一本化して特攻隊員になっている。
幸い、この日から12月14日早朝、丸山が台湾の新竹から比島に向けて進出するまでの約20日間の日記が残されているので、それにより、当時の彼の足取りを辿ることができる。
「11月21日、第201航空隊付を命ぜられ、本日発令された」とある。
特攻について語る場合、指名か志願かがよく問題になるが、丸山の当日の日記は「思いきや、光栄の神風特攻隊員として選を受け、司令官はじめ司令部の各位、筑波における各位の知遇を忝ふし、征途につくを得んとは」とあるので、約3ヶ月前に特攻を志願したという前提で、選ばれた(指名された)といえるのではないか。
「夜、水戸の小川(筑波空指定料亭)にて壮行会あり。筑波空準士官以上参加。今までになき盛会なり」とある。
筑波空から丸山と一緒に201空付きを命ぜられた者は、72期3名、予備学生13期7名、下士官14名で、彼ら全員の寄せ書きの写真がある。それには「轟沈」、「筑波特攻隊に続け」など書かれているので、彼らは201空への転勤が意味することを承知していたことがうかがわれる。丸山は、二番目に「馳参国難」と書いている。
「11月22日:筑波空を退隊、霞空(霞ヶ浦航空隊)に移動し、夜は多忙の中を割いて上陸、出征のことは実家へ通知する。山下方に一泊、父のもとに手紙を書く」とある。軍人である以上、常に死について考えていたとしても、死が現実に迫っていることを実感しながら、肉親に宛て手紙を書くときの気持はいかがであったろうか。
「11月23日:盛大な見送りを受け、霞空から空路鹿屋に移動。当地で17機を受領し、台湾の高雄まで空輸することになる。」
「11月24日〜26日:第22航空廠にて二日間で特殊爆装の工事を終わり、26日朝には進出可能の状態まで漕ぎ着けたが、天候不良のため、一日待機。」
「11月27日:「一旦、出発決意の後、離陸せるも、航法計画の疎漏と天候不良、加ふるに列機の結束全からず。竹島付近まで約40浬進出の後、悲壮なる決意の下に鹿屋に引き返す。神風特攻隊の出撃にも似て航空廠の工員、女子挺身隊多数の見送りを受けて出発せしからには、男一匹意地にも(悪天候を)突破して見せねばならないのであったが、竹島までつき従いたるもの僅か6機。何のための空輸か意味をなさないことになると判断すればなり」
引き返しには、よほどの勇気が必要であったと想像される。着陸後、直ちに研究会を開き、寄せ集めで空輸部隊を編成したときに起こりがちな現象が、丸山たちの場合にも発生したと結論。一致協力の重要なことを強調し、空輸を完璧に実施する決心をしている。」
「11月28日〜12月3日:天候の回復待ち。毎朝、鹿屋から定期で帰隊、弁当をもらい、天気図を見るといったことも日課のようになって、今日も取りやめかと思うと嫌になる」とあるが、このような状況下において、指揮官として隊員の気持ちが弛緩しないようにする苦労も大変であったと思われる。空輸にともなう諸要務、宿泊、食事、燃料の手配などの雑務を手落ちなくすることが空輸を円滑に実施する基本と割り切って、各所との調整に奔走している丸山の様子がうかがえる。
「12月4日:遂に空輸を決行した。全行程957浬。所要時間5時間50分という大飛行である。最初にして最後であろう空輸が、零戦をもってする飛行可能距離の限界に近いとは。夜は久しぶりにくつろいだ気持ち、バス(風呂)に入り、鹿屋以来の汚れを取り、ホッとする」
ちなみに零戦52型の航続距離は1,037浬である。搭乗員としての誇らしい気持ちと大事をやり遂げた後の緊張のほぐれた気持ちがよくよく表れている。
「12月6日:強風、豪雨を衝いて新竹に移動。よくも無事故で着いたと思われる節もないではない」とあるのは、悪天候のため、かなりの無理をしたことがうかがえる。「夜は早速新竹に遊ぶ」とあるが、長年、航空会社に勤めた筆者にとって、その気持ち、分からないでもない。
「12月7日:天候回復せず、午前は機体の繋止状況と各部の点検を実施。」
「12月8日:聖戦3周年の記念日を迎え、「今やレイテを巡る戦雲は、日一日と濃くなり行くことを覚えるのであるが、この難局打開の責任を双肩に担って、台湾に進出して来ている。我らに課せられた任務は重大であるとともに、極めて光輝に満ちた誇りであることを思うとき、生ける験ありの喜びを禁じ得ない。今日、新たにセブ方面に敵が上陸した。我らの一奮発がこの驕敵を撃破して、国家を、而して大東亜を泰山の安きに置き得ると思うと、男子の喜び、これに過ぎるものはない」と決意のほどを示している。
「12月9日:「天気回復。風強きも飛行作業を開始。何よりも商売道具の『降爆』より始める。経験が全くないので、要領を呑み込むには至らなかったが、案外やさしいもののようだ」とある。
男命の散るときは
当時の台湾における特攻訓練の教程は、次のとおりである(前掲書)。
第1・2日:発進訓練(発動、離陸、集合)
第3・4日:編隊訓練(出発時は発進訓練を併用)
第5・6・7日:接敵突撃訓練(出発時は発進訓練、編隊訓練を併用)
接敵法には高高度接敵法と超低高度接敵法の二つのやり方があるが、紙面の都合で割愛する。
「12月10日:空輸に協力した筑波空、姫路空の関係者が帰隊し、独り立ちしなければならない状態になった。心細い気持は隠すべくもない」と正直に認めているが、「結局最後は自分だけで判断し、実行もせねばならぬと思えば、前線にでるまでよい試練だ。実地訓練と思えば精もでる」と自身を励ましている。
「12月11日:10時までは、第一警戒配備」(空襲警報)」とあるので、当時、台湾もすでに戦場であったことが分かる。「昼近くより飛行作業開始。課目は哨戒体形と降爆。(降下角度が)浅い浅いといっているうちに、測定すると55°だった」とある。総員の練度向上がうかがえる。夕食前に自差修正を行っている。
「12月12日:雨天。午前中は雨の中で自差修正を行う。計算または修正法に自信なく、いわゆる勘によりメーキングすることは最も危険なり。修正後の残存自差に疑問あらば、冷静なる判断の下に、その原因を探求し、これを排除した後、正鵠を逸せざる修正を行うを要す」面倒だから適当にやろうというのではなく、きわめて慎重である。
「夕方より約2時間にわたり慰問演芸あり。神風特攻隊の歌も今までは俗悪なる響きを有する歌のみと思いおりしに、感慨を覚えつつ聴取せり」自分の置かれた立場により、身につまされるようになったのだろうか。
「12月13日:雨を衝いて訓練をするが、3回にて中止。午後上陸。夜に至り隊より急報あり。即ち、進出の令を告げ来る。遂に待望の秋は来た。明日、実動機のすべてを率いて出発の予定。0300(午前3時)に至るまで航路の記入などに過ごす。睡眠もまた大事。暫し休まんと床に就く」
丸山も人の子。戦地への進出に当たり、家族のことに思いを致したのは当然であろう。「静かに胸に手を当てて想いを昔のこと、郷里のことに馳せてみる。家には年老いたる父上が、今は子供らのすべてを家の外に出し、余生を過ごしておられる。母を亡くされて、一入子供たちのことを気にせられるようになったが、今頃はいかがなされたか。兄の戦死後、自分に対する期待も非常なものであったが、今度のことだけは心から喜んでくださることと信じる。忠兄(長兄)はじめ七尾の姉たち、大阪の姉上も、やがて来るべき報せには『隆、よくやった』と褒めてくださるに違いない」
死者の気持ちをあれこれと忖度することは、死者に対する冒涜であるかも知れない。しかし、このとき丸山は、日記に書かれたとは全く反対の事も暫時考えたのではなかろうか。悠久の大義に生きることと、肉親に対する情愛とは、まったく別の次元のものと思われてならない。
そして、14日の0330、丸山は遺書を認めている。巻紙に墨筆で水茎の跡麗しく書かれたその遺書は、台湾から七尾の丸山家に無事届き、その写真がある。
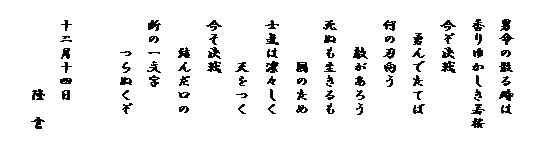 |
中学入学以来、兵学校、飛行学生、筑波空時代、そして最後の約20日間、几帳面に付けてきた丸山の日記は、ここで終わっている。
「死を見つめ 思いは何なりし 二十日あまり 彼の日記 遂にやむまま」
丸山の姉君、袋井幸子さんの歌である。
丸山が比島に進出してから、出撃した1945(昭和20)年1月5日までの彼の消息は不明であるが、元山空からマバラカット基地に着任し、後日丸山が所属することになる第18金剛隊の隊長・金谷真一大尉(兵学校71期)が、「搭乗員を引率して、みずからその先頭に立ち、指揮所から飛行機まで駆け足で行くと、それぞれの飛行機に搭乗し、バンドをかけ、諸計器を点検し、操縦桿を動かし、爆弾の安全装置を調べる。『出発発進』までの時間短縮のための訓練である。暑いのに飛行服を着て一斉に走って行く彼らの訓練は毎日続いた」(前掲書)とあるので、丸山も201空の一員として「出発発進」訓練に明け暮れていたのではないかと想像される。
米海軍中佐バートレット
後日、丸山とその人生の軌跡が一瞬交わることになる本篇のもう一人の主人公ウィルソン・バートレットは、1912(大正元)年、アメリカ中央北部のミネソタ州の農家に生まれた。
その後、バートレット一家はワシントン州に移住し、ウィルソンは大恐慌が始まった1929年に高校を卒業した。彼は、最初の2年間は働きながら土地の大学に通ったが、十分な学費が稼げず、退学のやむなきに至った。
しかし、幸運にもアナポリスにある海軍兵学校に年齢制限ぎりぎりで入校し、1935年6月、卒業と同時に少尉に任官(兵学校63期相当)、空母「サラトガ」(CV-3)に乗組み、丸3年を海上で勤務した。
1938年6月から、彼はフロリダ州ペンサコラ基地において飛行専修学生の生活を送り、1939年5月に待望の航空記章を取得した。当時の教官の一人が、後日彼が護衛空母「マニラ・ベイ」(CVE-61) に配属されたときのフィッフュー・リー艦長である。彼はこの間に中尉に昇進した。 一人前のパイロットになった翌1939年6月、彼は第2偵察中隊に配属されて空母「レキシントン」に乗組み、SBDドーントレスのパイロットとして活躍した。
そして2年後の1941年8月、重巡「チェスター」に水上偵察機4機とパイロット5名からなる重巡第5偵察中隊長として配属された。
同艦は11月28日、ウイリアム・ハルゼー提督の下、他の重巡2隻、駆逐艦6隻とともに海兵隊のF4F戦闘機12機をウエーキ島に輸送する空母「エンタープライズ」を護衛して真珠湾を出港した。
そして任務終了後の帰路、嵐に遭遇して入港予定が一日遅れたため、12月7日の早朝はオアフ島の西200浬の地点にあり、幸運にも日本機動部隊の真珠湾攻撃を免れることになった。
1942年1月、彼は大尉に昇進。1年3か月の重巡勤務の後、この年11月からワシントン州シアトル基地とカリフォルニア州エル・セントロ基地で勤務し、1943年5月、少佐に昇進した。
その後、カリフォルニア州サンディエゴ基地においてTBM/TBF アベンジャー雷撃機の練成訓練を受け、9月に訓練を終えたバートレット少佐は、TBFとF2それぞれ12機からなる第7混成艦載機部隊の飛行隊長として、翌10月、部隊を引き連れて就役したばかりの護衛空母「マニラ・ベイ」に初めて着艦した。そして2か月後の12月、同艦のエア・オフィサー(空母側の先任航空士官)に配置換えになると同時に、中佐に昇進した。
リー艦長は、南北戦争当時、南軍の総帥だったロバートE.リー将軍の末裔で、乗組員から敬愛されていた。「マニラ・ベイ」の乗組員は、その後リー艦長の指揮下で、1944年1月に実施されたマーシャル諸島の占領を皮切りに、ビスマルク諸島、東部ニューギニア、マリアナ諸島の侵攻作戦に次々と参加したが、武運に恵まれ、1945年1月5日、丸山機が突入するまでは、特筆すべき損害を蒙ることはなかった。
1945年1月5日
1944年10月17日と翌18日にわたり、レイテ湾内の小島スルアン島などに対して周到な上陸作戦の下準備をした連合軍は、10月20日、その膨大な海空戦力による熾烈な砲爆撃の後、圧倒的な兵力をもってレイテ島に本格的に上陸した。これを迎え撃つ日本軍の健闘にもかかわらず、日本軍は初日目において水際陣地を突破され、タクロバン飛行場も奪取された。日本軍のレイテ作戦は、その上陸防御戦闘の初動において組織的戦闘力を失い、その後のレイテ決戦へと発展して行くのである。
そして戦局は、12月27日、参謀本部・軍令部両総長が、今後の作戦指導として、レイテ島における決戦の断念を天皇に上奏するとろまで悪化した。この間に、連合軍は12月15日、レイテ島の北西300浬にあるミンドロ島にも上陸を敢行した。
年明けの1945年1月2日、フィリピン群島最大のルソン島攻略のため、約20万の連合軍がレイテ島から出撃、上陸地点リンガエン湾に向かって続々と北上を開始した。ここは3年前、日本軍が比島を攻略したときに上陸した地点である。
この攻略の先鋒部隊は、旧式戦艦6隻、巡洋艦10隻、護衛空母12隻、駆逐艦10隻と掃海艇63隻を含む164隻の大部隊であった。日本軍には最早昔日の戦力はなく、特攻隊による微弱な反撃以外に手段がなかったのである。
1月5日、ミンドロ島と、その西側のカラミアン諸島の間にあるミンドロ海峡を通過し、マニラの南西に到達した梯団に対して午前中2回の特攻が行われたが、護衛空母から発進した要撃戦闘機に阻まれて戦果を上げることができなかった。
この日の午後、丸山の所属する第18金剛隊がマバラカット基地から発進し、この梯団を攻撃した。
連合艦隊告示第85号戦闘経過概要によると、第18金剛隊は、隊長金谷真一大尉が第1中隊長と第1小隊長を兼務、攻撃(爆装)8機、直掩2機、同様に丸山が第2中隊長と第1小隊長を兼務、攻撃(爆装)8機と直掩2機、計20機の零戦からなっていた。
「1557ルバン島西方北上中の敵大攻略部隊攻撃のため、「マバラカット」を発進。
1716 (索敵線の)先端、敵を見ず。
1730敵を認む。小型輸送船、舟艇多数。攻撃隊3機小型輸送船に命中、轟沈。他に1機命中せるものの如く、白煙上がるを見る。
1845細川機(第1中隊・直掩)「マバラカット」帰着。
下川機(第1中隊・直掩)、中野機(第2中隊第2小隊・攻撃)故障、直ちに引き返す」とあり、残り全機(17機)が未帰還」になっている。
丸山が率いた第2中隊の直掩は、彼のクラスメート北川直隆中尉を含む2機とも未帰還になったため、第2中隊の戦果は、報告されなかったのであろう。記事として、「直掩機少数にして一部の戦果を確認し得たるのみにて、他の機も概ね成功せるものと認む」とあり、丸山機の「マニラ・ベイ」突入に関しては、201空本部に伝わっていない。
丸山機の飛行コース推測
米側の資料によると、丸山機の突入は1748(日本時間。以下同じ)である。すなわち、マバラカット発進後、1時間51分を要したことになる。しかし突入地点は、直航では30分そこそこで到達できる距離なので、残りの1時間20分をどのようなコースで飛行したのだろうかという疑問が生じる。
直掩機が未帰還になったので、丸山中隊の飛行経路について知ることはできないが、この空白の時間を説明できそうな経路を再現することは可能である。
告示によると第18金剛隊の発進時刻は1557なので、彼らが出撃命令を受領したのは、おそらく1530以前であったと思われる。1600頃に発進すれば、1700までには会敵できる。敵部隊の航跡図から、その1700の予測位置を判断し、マバラカットと結ぶと約250°である。
もし、このコース上に目標を発見できなければ、捜索線の先端180浬(気速180節で1時間の距離を設定)で右90°旋回し340°のコースでドッグ・レグを30浬飛行する。このコース上にも敵影を見なければ、再度大きく右旋回して080°のコースを飛行すれば、日没(1840)までにはマバラカットに帰着できることになる。
マバラカットの滑走路は、北東〜南西に一本設置されている。この日、丸山たちは南西側から北東側に向かって離陸したことであろう。発進時刻は1557となっているが、第一中隊が30秒間隔で発進したとしても、全機が発進し終わるには5分を要するので、丸山の実際の離陸時刻は1602以降であったと思われる。
離陸後、旋回して編隊を組み、250°のコースに乗って巡航高度に達するまでにも若干の時間を要したであろう。
飛行時間の算出に当たって、当日の上層風は45°40節を使用した。これは当日、海上において風向風速は、北東20〜30節という記録があることによる。出航コースは250°、右後方からの追い風を受けて対地速度は215節に増し、この状態で飛行して24分を経過した1621、「マニラ・ベイ」は丸山機の左下方約10浬の地点にいたはずであるが、丸山はこれを発見していない。
当日の天候は、すでに雨季は終わっていたが、雲量6以上の曇天だったのではないか。ちなみに計算ではあるが、高度1,500フィートから見える距離は約75浬、1,000フィートでは60 浬である。
離陸から50分を経過した1647、出航コースの先端に到達するが敵を見ず。90°右旋回してコース340°に乗る。この レグ は、 出航コースと入航コースとの開きが10°なので30浬になる。ここでは右前方からの向い風となり、対地速度が155節に落ち、飛行するに要する時間は12分、やはり会敵せず。
再度右に約90°変針して入航コース 080°に乗ると、今度は左前方からの向い風となり、対地速度148節の飛行になる。そのまま飛行を継続して39分を経過した1738、丸山は「マニラ・ベイ」を発見、攻撃に移ったことであろう。丸山機の発進から突入までの時間は 1時間51分 で、計算との間に10 分の誤差があるが、前述の離陸順番待ちなどを考慮すれば、これは、航法上の許容誤差範囲内といえるのではないか。
偶然の一致かも知れないが、「マニラ・ベイ」の戦闘詳報には、特攻機は太陽を背にして低空で本艦の左舷真横(進路は真北。従って西側)から接近したとある。しかし、これはあくまでも他機の索敵攻撃を参考にした筆者の臆測であり、その根拠となる資料はない。
危機一髪のマニラ・ベイ
丸山たちが「マニラ・ベイ」を発見した後の攻撃は、次のとおりである。
1743、2機の特攻機が護衛空母「マニラ・ベイ」を攻撃した。特攻機は爆装した零戦で、そのパイロットは、リー艦長によると、驚くばかりの熟練した操縦技術の持ち主であったという。彼らは、ときには海上100フィート以下の高度を若干蛇行しながら飛行し、目標の900メートル手前まで接近した。
一機目の零戦は、突然急激に上昇し、高度800フィートで反転、切り返して高速度で機銃を掃射しながら突っ込んできた。
そして、「マニラ・ベイ」の上部構造物の基部と前方エレベーターの中間に体当たりした。機体は飛行甲板を突き抜けながら二つに折れ、抱えていた爆弾は格納庫甲板で炸裂した。
その爆風は、飛行甲板に5メートル四方の穴を開け、そこから激しく噴き上げて、バートレット中佐を含め、艦橋にいた大半の者を横薙ぎにした。彼らは、ひどい日焼けのような火傷をした。さらに爆風により、レーダー室にいた全員が焼死、近くの無線室に火災が発生して通信機能は決定的な打撃を受けた。パイロットの待機室は、灼熱した爆弾の破片で火災が発生した。 一機目の特攻機の約15秒後、二機目も空母の近くで一機目と同様な「空中バレエ」を演じ、機体を急速に傾けて突入したが、機転の利く乗組員が、強烈なサーチ・ライトで特攻機の飛行経路を照射した。
そのために幻惑されたのか、または猛烈な対空砲火のためにパイロットが負傷、または機体が損傷したのか、この二機目は「マニラ・ベイ」の飛行甲板を掠るように横から接触し、片翼で無線アンテナと右舷桁端を切断して10メートル離れた海中に回転しながら落下し、喫水線付近で衝撃により爆発したが、爆風による被害はほとんどなかった。
一機目の特攻機により、突入箇所近くの格納庫甲板に駐機し、燃料を満載、爆弾の搭載も終わっていたTBF は、すぐさま燃え上って火炎に包まれ、近くの航空機も類焼して、艦内が大火災になる危険が迫ってきた。もし、リー艦長が僚艦「オマニー・ベイ」(CVE-79 )の生存者の貴重な体験に基づく忠告を聞き入れず、予防対策がとられていなかったならば、「マニラ・ベイ」は喪失していたかもしれない。
1月4日の夕刻、「オマニー・ベイ」は、特攻機の攻撃を受けて沈没した。その主因は、格納庫内の火災発生後、それを迅速に消火できなかったので、燃料や爆弾を搭載、待機していた航空機が次々と誘爆したからである。
リー艦長は、彼らの忠告に従い、特攻機の突入による衝撃が発生する直前、スプリンクラーとウオーター・カーテンを作動させるスイッチを取り付けた。そして、そのスイッチを入れたのである。艦長のこの対策が艦を救ったといえる。
特攻機の爆弾が炸裂した5秒後には「マニラ・ベイ」の消火装置は作動し始めて格納庫内は水浸しになり、火災は発生したが、火炎が燃え上がるのを抑える役目を果たした。また、石綿の防火服と呼吸装置を着用した消火隊員も水、霧、フォームを散布して懸命に消火に勤めた。
その結果、特攻機が突入してから1時間後に火災は制御された。スプリンクラーとウオーター・カーテンの給水は止められ、操舵機も正常に復旧し、1900までに「マニラ・ベイ」は編隊の所定の位置に戻った。
そして、2300までかって消火に使用した海水を排出し、4度の右舷側への傾斜を回復させた。僚艦とは、オルジス・ランプと飛行甲板に駐機していた無傷のTBF に搭載されている超短波無線機を間に合わせに使用して通信連絡に当てた。レーダーは、送信室が完全に破壊されたので、修理不能であった。
「マニラ・ベイ」が特攻機の攻撃を受けていたとき空中にいた8機の同艦所属機は、臨時に僚艦に着陸していたが、「マニラ・ベイ」に帰投した。さらに僚艦の補用機のうちから喪失した TBF 8機の埋め合わせと F4F 2 機が供給されたので、バートレット中佐は、48時間以内に制限があったが、航空作戦を再開できた。そして1月9日の上陸作戦実施日には、「マニラ・ベイ」から延べ42機が攻撃に参加している。
消火作業中、乗組員の一人が特攻隊員の財布を拾得し、バートレット中佐に提出した。一段落してところで、彼は艦長たちと中身を改めたが、日本語のできる者が現場にいなかったので、財布は彼が保管し、後日、然るべきところに翻訳を依頼することが決まった。
爆弾の炸裂により飛行甲板に生じた破壊口から少し離れたところで発見された特攻隊員の遺体は、飛行服の上から寄せ書きをした旗を腹に巻き、署名入りの白い鉢巻を締め、さらに45 cmくらいの短い軍刀(短剣?)を持っていたとリー艦長は証言している。
翌6日、彼の遺骸は「マニラ・ベイ」の14名の戦死者(他の1名は爆風で艦外に吹き飛ばされて行方不明)と共に水葬に付された。リー艦長の南部人としての貴族的な考え方が、敵兵とはいえ特攻隊員の勇気を讃たえ、部下の中に猛反対する者もいたことは想像に難くないが、その遺骸を水葬に付したのではないだろうか。
リンガエン湾の上陸作戦が終わった1月17日、「マニラ・ベイ」は米本土で修理をするため、比島海域を後にした。そして沖縄作戦に間に合うよう、原隊に復帰した。
あの特攻隊員は誰か?
翌2月、バートレット中佐は「マニラ・ベイ」を退艦し、サンディエゴにある西部艦隊航空隊に転出を命ぜられた。彼の太平洋戦争は、ここで終わったのである。
そして1946年、リー艦長たちとの話し合いどおり、海軍省あてに特攻隊員の遺品の翻訳を依頼した。
しかし、数か月後に返却されたのは内容物の写真とその訳文だけだったので、彼は現物の返却を求めたが、戦利品は、すべて合衆国政府に没収されるとのことで、当局に冷たく拒否されたという。
バートレット中佐は戦後も米海軍に勤め、外地勤務もあったが、日本に来る機会はなく、大佐で退役し、その後は首都ワシントン郊外で悠々自適の生活を送って、1982年に死去した。特攻隊員の遺品の写真などは、バートレット大佐の遺品の「経歴不可解」と上書きされた封筒に保存されていた。
息子のバートレット教授にも、日本に来る機会はなかった。このようにして、バートレット家の人々にとっては、特攻隊員の遺族を探す機会がなく、半世紀近くの歳月が流れて行ったのである。
ところが1993年、孫のレイモンド青年の言葉を借りれば、「突然の偶然」による転機が訪れた。彼が大学を卒業し、語学補助教員として日本で就職することになったのである。任地は鹿児島県国分市、期間は2ヵ年。これでバートレット家と日本の繋がりができたわけである。
そうこうするうちに、またもや「突然の偶然」が起きた。彼は、英国留学から帰国したばかりの伊地知希さんと知り合った。そして二人の仲は急速に進展し、結婚するまでになったのである。
1995年6月下旬、バートレット教授夫妻は、伊地知夫妻と希さんに会うために来日した。そのとき、父親の死後13年間、父親の残した封筒の中で眠っていた特攻隊員の遺品の写真を持参し、レイモンド青年の義理の両親になる伊地知南氏と夫人の和枝さんにその写真を見せ、その隊員の遺族を探して欲しいと話した。戦争を知らず、ましてや特攻隊とは全く無関係だった夫妻にとっては、正に晴天の霹靂で、探せと言われても、どこからどう始めればよいのか。次の写真(掲載略)を見ながら、夫妻は途方に暮れたことであろう。見たところ、とりあえず手がかりになるのは、増田脩少尉の名刺だけである。
1) 父親と思われる羽織袴姿で椅子に腰かけた初老の男性
2) 母親と思われる白い割烹着に「大日本国防婦人会」のたすきをかけた中年の女性
3) 戦闘機の前に立つ飛行服姿の若者(後日、兄の寛陸軍中尉と判明)
4) 白地左下方に8行の文字が書いてある日章旗(判読困難)
5) 海軍少尉増田脩の名刺(右肩に「第201海軍航空隊付」と所属部隊名が手書き)
6) 磁気羅針儀自差修正法の公式表
7) 公務運賃割引証(未使用申請用紙)
このとき伊地知夫妻は、教授夫妻を鹿屋にある海上自隊航空基地史料館に案内した。ここには海軍関係の特攻戦死者の名簿がある。館長菊池利昭3等海佐はじめ、史料館側の全面的な協力にもかかわらず、この日分かったことは、前出の名刺から、増田少尉は名古屋市長田町(現長田区)、名古屋高等工業学校出身の第13期予備学生で、1944年12月1日海軍中尉に進級し、第15金剛隊長として1944年12月29日、バタンガスから出撃していることだけであった。
ここで問題になったのは、増田中尉の出撃日は12月29日となっているのに対し、「マニラ・ベイ」が攻撃されたのは、翌1945年1月5日であり、その間に約1週間の差がある。したがって、増田中尉は探している特攻隊員ではない可能性が多分にあるということであった。
夫妻たちの史料館訪問を取材した鹿児島TV局からもその様子を放映してくれたが、放映区域が鹿児島地方に限られていたためか、何の反響もなかったとのことである。
手がかりは日章旗の文字
バートレット教授夫妻は、約10日間滞在の後帰国した。レイモンド青年と希さんは、8月上旬アメリカに引き上げるので、その準備や諸手続きに忙殺され、特攻隊員探しは、もっぱら伊地知夫妻の仕事になった。
さっそく、伊地知氏は岡崎市在住の知人、小倉喜八郎氏に増田中尉の遺族探しを依頼された。長期間かかるのではないかとの予測に反し、10日あまり経って小倉氏から、増田中尉の令弟、増田澄氏が春日井で開業医をしていることが判明した旨の連絡があった。
増田氏は、それまでに知り得た兄脩中尉についての情報とは若干違うとは思いながら、7月下旬、小倉氏とお会いになった。
しかし、増田氏にとって写真の本人や両親と思われる人々にはまったく見覚えがないので、該当する特攻隊員は増田中尉ではなく、名刺は、交換したものをその特攻隊員が持って出撃したのであろうということになった。
伊地知氏や小倉氏にとっては、折角の期待が裏切られる結果になり、調査は振り出しに戻ったのである。筆者の経験からしても、このような調査は一筋縄では行かないものがあり、絶えまざる努力と一種の勘を要するものである。
伊地知氏によると、夫人の和枝さんは、写真の日章旗の文章にこだわられたそうである。通常、兵士が出征する前に家族、友人、知人などが寄せ書きする場合、日の丸から白地の部分に放射線状に書くもので、もちろん、それぞれの筆跡が違う。
しかし、この日章旗は寄せ書きにしては文字が少なく、一隅に片よって、しかも筆跡が同一人物のものであることに気付かれた。
8行からなるこの文章は、判読不能な部分が多々あるものの「二十有三年の御慈愛溢るる御養育」で始まり、「昭和十九年十二月二十一日」の日付、そして「不肖○書」となっている。この形式であれば、最後の行の「不肖」と「書」の間の文字が書いた本人の名前に間違いなく、この場合は一字である。鹿屋航空基地史料館でもらって来た1月5日に出撃した特攻隊員の名簿から、名前が一字の隊員を探していくと、啓、肇、博などの候補から、おぼろげながら形が一番似ているのは「隆」で、丸山隆中尉ではなかということになった。
早速、伊地知氏は簡単な手紙を七尾市在住の丸山中尉の遺族宛てに書き、祈るような気持ちで投函された。
数日後、丸山中尉の甥に当たる丸山忠範氏から返事が来た。それには戦後50年を経た今日、叔父隆中尉の遺品の写真が届いたことに対する驚きと喜びが余すところなく書き綴られていた。
そこで、伊地知氏は、これまでの経緯を詳細に記し、バートレット教授から預かっていた写真全部と、調査の段階で入手された「マニラ・ベイ」が特攻機に攻撃されている写真などを添え、速達で送られた。それらは、丸山中尉50回忌の盆の直前、忠範氏の手元に届いた。
丸山中尉の兵学校時代の同期生、泉五郎氏の言葉を拝借すれば、「軍神 丸山隆君の凱旋」である。このときの感激を姉君の袋井幸子さんは、次のように詠んでおられる。
|
奇しき因縁の 遺品を映す 温情は 敵艦より来る 辿りて至る 五十年目に 帰り来し霊 特攻散華の「隆」の日の丸 |
*
伊地知氏と丸山忠範氏からバートレット教授に送られた丸山中尉を特定するに至るまでの数々の資料は、英訳されないままで更に十数年の歳月が流れた。しかしこの間、バートレット教授は、機会があれば丸山中尉と父親のことを書いて発表したいと常に考え、知人にもそう話していたようである。
特攻機が護衛空母「マニラ・ベイ」に突入してから半世紀余を経て、バートレット家の三代にわたる人々の厚意と、伊地知夫妻の尽力により、奇跡的にその特攻隊員は丸山隆中尉と判明し、遺族にも連絡できていた。
しかし、バートレット中佐が同艦上で部下から受け取り、1946年、合衆国海軍当局に提出して内容物の翻訳を求めたという丸山中尉の財布と中身の現物は、今もって返還されておらず、どこにあるのか不明という。
丸山中尉の遺品が発見されて故国に帰還し、バートレット教授の戦後に終止符が打たれることを切に願ってやまない。
最後に、本篇を書くにあたってお世話になった丸山忠嗣氏、伊地知氏ご夫妻、バートレット教授、文中にお名前が出てくる方々に、この場をお借りして厚くお礼申し上げたい。
参考文献:
「特攻」森本忠夫・文芸春秋
「ああ、神風特攻隊」安延多計夫・光人社
「回想の大西滝次郎」門司親徳・光人社
「神風特別攻撃隊の記録」猪口力兵・中島正・雪華社
「桜花・非情の特攻兵器」内藤初穂・文芸春秋
「特別攻撃隊」特攻隊慰霊顕彰会
「筑波海軍航空隊―青春の証―」友部町教育委員会
「戦史叢書・西部ニューギニア方面陸軍航空作戦」防衛庁防衛研究所戦史部・朝雲新聞社
モシターンガイド2005 7月・8月号、終戦60周年記念特集:
その一「甲板に散った特攻隊員の遺品をめぐる日米兵士の物語」伊地知
南
その二「戦争をはさんだ二つの家族、若者は何を伝えたかったのか」伊地知
南
「軍神 丸山隆君の凱旋」泉 五郎・海軍兵学校第72期ホーム・ページ
「兄の遺品」増田 澄・海軍兵学校第72期会報「なにわ会ニュース」第84号
連合艦隊告示第85号
戦闘経過概要
The
USS Manila Bay (CVE-61) After Action
Report
The
USS Manila Bay (CVE-61) War Damage
Reports
The
Kamikaze’s Wallet, Randolph Bartlett & Kan Sugahara(USNI, The Naval History
Magazine に来春掲載予定)
Emails:
Don Kehn, Jr. (A Blued Sea of Blood, Zenith Press 著者) and Kan Sugahara
Emails:
Tony Tulley (Shattered Sword, Potomac Book, Inc.共著者)and Kan Sugahara
Emails: Wilson R. Bartlett, Jr. and Kan Sugahara