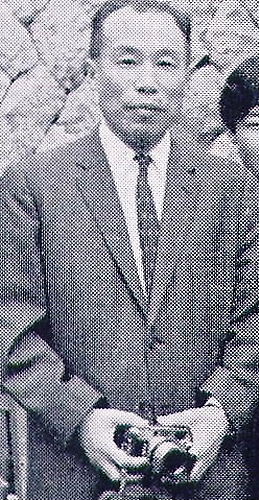 |
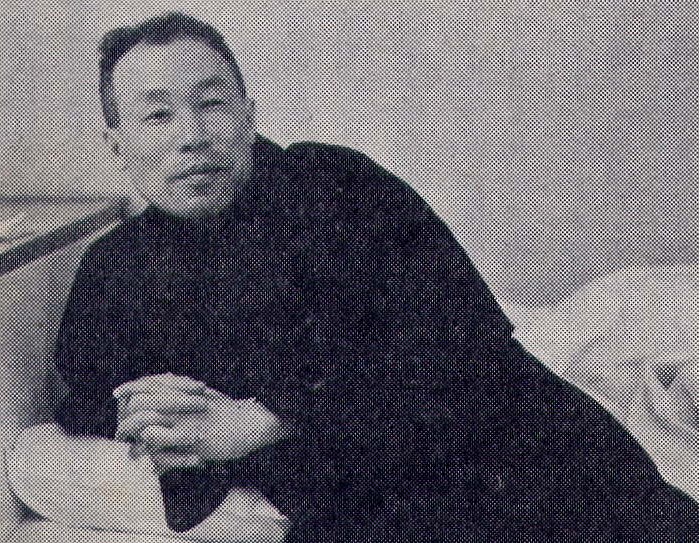 |
平成22年5月15日 校正すみ
村島保二君追悼記
平田 隆一
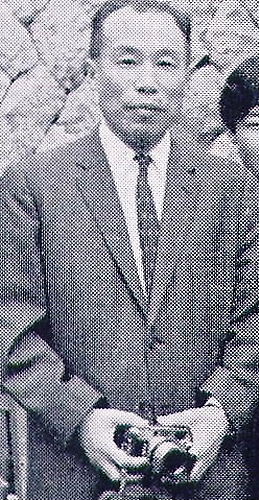 |
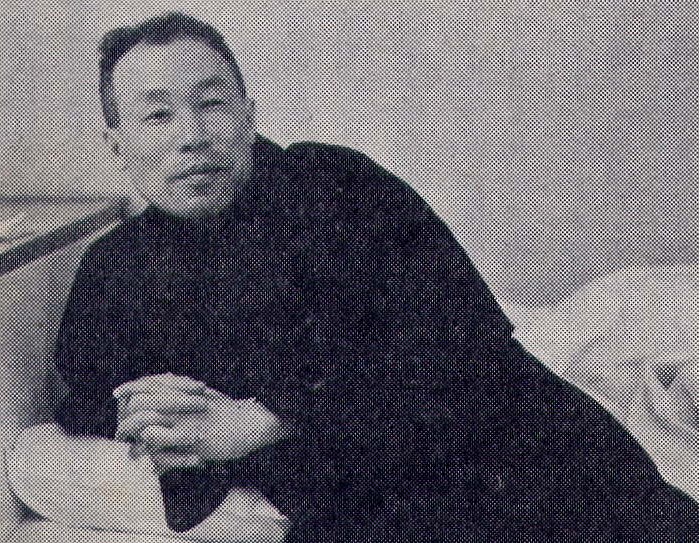 |
3月11日の朝、いつもの通り出勤して、席に着いていると、机の上の電話器のベルが鳴り出した。受話器を耳に当てると、「白根様からお電話が入っております」と交換手の声、白根とは随分久し振りだが、一体何の用だろうと、待っている私の耳に、白根の声が飛び込んで来た。
「村島が亡くなった。今晩自宅でお通夜だ。俺も行きたいが、今忙しくて、とても行けそうにない。貴様は博多だから、何とかなるんじゃないか、クラス代表として行ってくれないか。香典については、小灘からそちらに電話があると思う」。
「うーん」と思わず唸ってしまった。村島についての、いろんな思い出が次から次へと頭の中を物凄いスピードで、飛び交って行く。ああしまったな、せめて生きている内にもう一度だけでも会っとくんだったな。折角九州に転勤して来たのに、何時でも会えるなんて、横着していて済まなかったな、悪かったな、と独りで悔んで見たが、どうにもならないことだった。
丁度その日は佐世保に出張する予定であったので、佐世保での用事を早々に済ませて、車を飛ばして長崎に向った。車中で長崎市内地図を拡げて、名簿の住所を手掛りに探した。地図の上では意外と判り易い処にあった。ここで又口惜しかった。もっと早く元気の時に来て慰めてやれば良かった、申し訳ないと独りで詫びたものだった。
車から下りた時は、もう薄暗くなっていて、人通りもないし、地番の標識を頼りにようやく探し当てた。玄関には花輪が立て掛けてあり、沈み込んだ空気が周囲を包んでいた。いきなりづかづかと上って行きたいような、もどかしい昂ぶった気持をようやく押えて、案内を乞う。玄関の土間には弔問の客の履物がびっしりならんでいた。
「私、兵学校第72期の平田隆一でございます」と思わず玄関で怒鳴ってしまった。何か無性に腹立たしかったことを、今でも思い出す。
あれだけの大戦争を生き抜いて来ておりながらまだこの若さで、たとえ病気とはいえ、むざむざ死んでしまうなんて、口惜しくて、口惜しくて、たまらない気拝だった。仏前でお線香を上げながら、思わず涙が、あとからあとから溢れて出て来て、どうしようもなかった。
村島とは四号、三号時代を同じ24分隊で暮した仲である。名にし負う赤煉瓦の生徒館である。夜な夜な、凄絶果敢なる猛修正を喰らった仲である。
村島はクラスの先任だし、良く勉強もしていたが、時々隊務のへマをやっては、一号生従から怒鳴られて、共同責任の罪(?)に問われて、四号全員整列を掛けられては、お達示を喰らい、見事に殴られたものだった。
初めの内は、あいつさえしっかりしていればこんな目に会わなくても済むものをと、内心怨らんだものだったが、その内に村島という男の真価が判って来た。底抜けに邪心のない純真な男なんだ、悪気があってやったんじゃない、素朴な失敗だし、それを皆がカバーしてやらないのがいけないのだと、段々に判り合うものができて来た。自然と四号同志の団結というか、お互いに仲良くなって来るという気風が湧いて来た。これをしも彼の人徳という。一号生徒の指導の狙いも、そういう処にあったのか、ある意味では一号生徒も振り廻されていたのかも。かくして四号は日夜鍛えられて行った。
そういう裏の動きなどまるで無頓首に、ご本人は相変らず天衣無縫に振舞って、時々われわれをズッコケさせたものだった。ある意味では童子のように、幸せな男かも知れない。
二号、一号時代は分隊も教班も離れてしまい、生徒館の中でも、めったに会うこともなかった。卒業して、私は飛行学生となり、彼は艦船に乗組み、更に更に離れて行った。普通このようなケースでは、絶対にといって良い程、再び会うことはないはずであるが、運命の神は二人に再会の機会を与えてくれた。
昭和20年4月、当時私は天山艦攻の偵察員として、攻撃251飛行隊所属となり、鹿児島県の串良基地にいた。4月28日飛行長足立少佐(65期)に呼ばれ、風変りな命令を貰った。
「笠野原基地に行き、戦闘機隊の誘導機となり、敵機動部隊の上空まで、戦闘機を誘導せよ」というのである。
笠野原基地は直ぐ隣で、行って見ると、小林晃がいた。彼とは四号、三号時代、同じ24分隊だったし、霞ケ浦で別れて以来、初めての再会で彼は戦闘機に、私は偵察専修にと別れて行ったのだった。
その彼を、私が敵機動部隊の上空まで、誘導することになった訳だ。お互いにその奇遇を喜び合い、健闘を誓い合った。その日は、敵の情報がまだ入って来ないので、一応宿舎待機となり、小林の都屋に行き、ベッドに腰掛けて、クラスのこと、先輩のこと、あれこれ一別以来の出来事を、次から次へと、機関銃のように、お互いに喋りまくった。そこへ呼びにやった村島が入って来た。村島はその後兵器整備学生の教程を経て、当時戦闘機の機銃整備の分隊長をやっていたのだった。
お互いに、四号、三号時代を思い出して、また一しきり、話の花が咲いた。狭い粗末な兵舎の中のベッドの上だったが、クラスの者がしかも四号時代を一緒に暮した者が三人も一つ処に、たとえ暫らくの間でも語り合えたことは、大変な喜びであった。われわれにとっては、大変懐かしい語らいであった。しかし、今この楽しかったことを思い出せる者は私一人となって⊥まった。
結局この作戦は一部修正され、私の任務は解消となり、串良に戻ることとなった。それから約1か月後に、小林晃はB29の迎撃に出て、帰らなかった。
それから、終戦。
昭和21年5月、私は九州大学の土木工学科の1年生となった。ある日、大学の構内で、角帽姿の村島を見掛けてびっくりした。向うもびっくり、彼は機械工学科に入学した。構内の芝生に腰をおろして、一別以来の思い出や、近況を語り合った。元気な姿を見たのはそれが最後であった。時折バイパスニュースで消息は知ってはいたが。
あれこれ思い出に沈んでしまっていた。不図吾にかえると、義兄と名乗る人が、いろいろ話しをして下さっているようであったが、頭がガンガンして、いや良く聞き取れなかった。最後に、顔を見てくれといわれ、棺の顔の部分の蓋を取り、村島の死に顔を見た。うっすらとヒゲが伸びて、まるで眠っているような、やすらかな顔であった。四号時代と全然変っていない、あどけない童顔のままで、少し出っ歯の処もそのままのやすらかな顔であった。思わず又涙が溢れて来た。村島よ、いろいろなことがあったな、苦労もしたろうな。村島よ、さようなら。安らかに眠ってくれ、さようならと合掌してお別れした。
暗い坂道を電車通りまで歩いたが、泣けて、泣けて、しようがなかった。
父のこと
村島 温子(長女)
父のことで想い出すことといえば、父のいい面はかりで、逆に私たち家族の父に対する態度に後悔の念をおぼえてしまいます。脳腫瘍という、どうしようもない病気になってから9年間、何度も入院、手術を繰り返し、その当時としては自分でも父のことを精一杯にいたわった積りだったのですが、今になって考えてみると、もっともっと理解してやるべきではなかったかと思ってしまうのです。
この病気は、一般には、非常な苦痛を伴って、気狂いのように暴れる、という風に思われているようですが、父の場合は全くそのようなことがなく、とても穏やかで、ほとんど「痛い」と言ったのを聞いたことがありませんでした。
それで私たちもそれほど気にすることもなく、毎日が過ぎていったのですが、日記には(後になって分ったことですが) 時々『頭痛』という文字が書かれてありました。何といっても、患部は頭なのですし、その手術となれば、どんなにか、恐怖であり、不安であったろうかと思われます。そして苦痛は所詮本人のものでしかない、自分以外の人は真に分ってもらえないものではありますが、家族の私たちにさえ言わなかったというのは、私たちにとっては淋しいことです。
けれども反対に、それが父の強さであり、私たちに対する思いやりだったのでしょう。
父は昔から、特に母と娘の私には、優しかったのですが、病気をしてからは一層優しくなりました。ですから、笑顔は思い出せるけれど、怒った顔は浮かんできません。それに他の方に対しても、少しも面倒くさがることなく、誰にでも声をかけることを忘れなかったようです。父の亡くなった後、思いがけない方から、父のことを「いつも声をかけてもらって…」などと言われることもしばしばで、改めて感心しています。
何に対しても一生懸命だった父、気を抜くことのできない不器用な父でした。
× × ×
72期級会様
村島田鶴子
謹啓 先般 夫保二儀死去に際しましては、早速ご懇篤なるご弔詞並びにご香料を賜わり、またご多用中にも拘りませず遠路態々ご会葬いただき、ご芳情の程誠に有難く存じます。
また、8年余の度重なる療養中にはお励ましのお言葉並びにお見舞をいただき、ここに生前のご厚誼と併せて心より謹んでお礼申し上げます。実は拝顔の上、お礼申しあぐべきでございますが、略儀ながら書中を以ってご挨拶申し上げます。
なお、ご香典返しの儀は勝手でございます、皆様方からお寄せいただきましたご厚志の一部を、うさぎ会と三和みのり園(編注、児童福祉施設団体)に寄贈させていただきましたので、何卒ご諒承の程お願い申しあげます。
。(なにわ会ニュース31号6頁 昭和49年9月掲載)